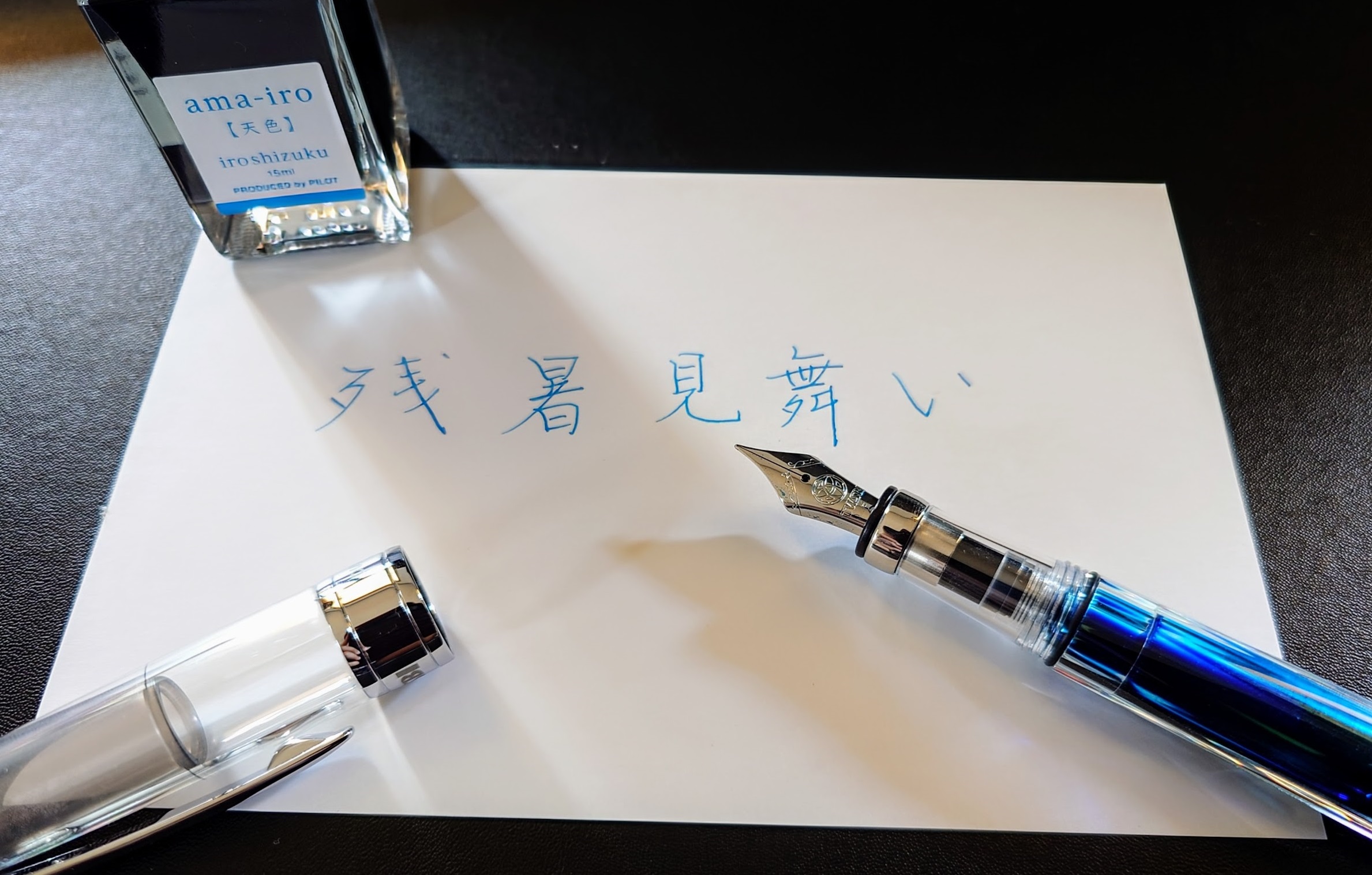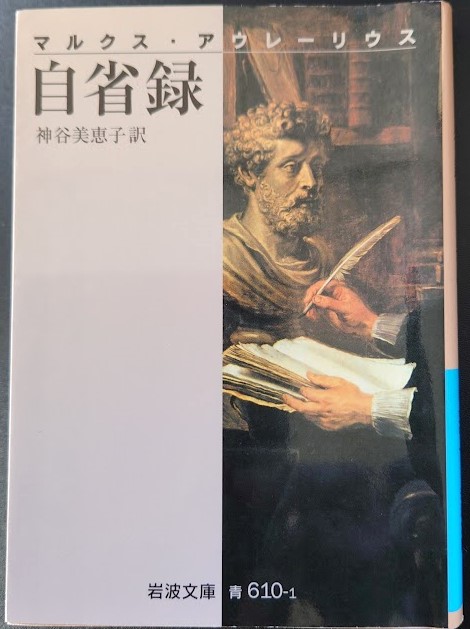【今年の一枚】先月自転車で小豆島の寒霞渓を上った際の一枚です。上り坂は非常に辛い道のりでしたが、頂上からの眺めは疲れを忘れさせてくれるものでした。
年の瀬、皆様いかがお過ごしでしょうか?
振り返ると、バタバタと忙しくて、あっという間の一年ではありましたが、色々勉強になることも多かったなと思います。そこで今年苦戦した登記について備忘録的にまとめておこうと思います。
問題となったのは所有権移転仮登記の抹消登記でした。
仮登記って何?という方のために簡単に説明すると、対抗力などは認めらない、順位の保存のためになされる登記のことで、登記の原因になる実体法上の権利変動が既に生じている場合(1号仮登記)と、権利変動がまだ生じていない請求権の段階のもの(2号仮登記)があります。
2号仮登記は、売買の予約をした場合や、農地で売買契約はしたけれど農地法の許可がまだ得られていないといった場合に使われます。
これに対して1号仮登記は、権利変動自体は既に生じているけれど、登記に必要な権利書を添付できない場合などに使われます。
1号も2号も、仮登記のままでは、登記としての本来の効力は発揮できません。所有権の登記であれば、所有権を第三者に主張したり、抵当権であれば、これを実行して競売にかけたりといったことをするには、事前に仮登記を本登記にする登記手続きが必要になります。
さて、今回は相続のご依頼を頂き、登記事項を確認したところ、土地の一つに、贈与を原因として所有権一部移転(持分10分の1)の仮登記がされておりました。土地の所有者も、仮登記の名義人も既に亡くなっているので、何故このような仮登記をしたのかは不明ですが、このままでは、完全な所有権を取得できない可能性があり、この土地を売ったりといった処分を行うことが困難になってしまいます。そのため、相続登記と併せてこの仮登記の抹消登記手続きも請け負いました。
仮登記された権利も当然相続することができます。1号仮登記は権利変動が既発生ですので尚更です。そこで、仮登記名義人の相続人の方々に協力頂き、遺産分割協議により仮登記の相続をして、相続した仮登記名義人から仮登記の抹消登記を行っていただくことにしました。相続登記は遺産分割協議書中にどの仮登記を相続するのかをしっかりと特定できるように記載する事に注意すれば普通の相続登記と何も変わりません。
そして、相続した仮登記の抹消ですが、仮登記は対抗力が認められていないため、簡易な抹消手続きが認められています。通常登記は両当事者、権利者と義務者が共同で申請することが原則とされています。権利者=抹消登記で利益を受ける所有権者。義務者=抹消登記で自らの権利が消えてしまう仮登記名義人。の両方が協力して登記するのが基本です。
しかし、仮登記に限っては、いくつか例外が用意されていて、
① 仮登記名義人からの単独申請
② 仮登記名義人の承諾を得て、権利者からの単独申請
が可能となっています。
さてそんな訳で、仮登記の相続登記と抹消登記を申請することになりますが、ここに落とし穴があります。それは、『相続した仮登記だけを抹消すると、相続以前の仮登記に戻ってしまう』という点です。
どういうことか、理解頂くにはまず、前提知識として、『1号仮登記の移転登記は主登記』でなされます。主登記というのは新たな順位番号を付す登記のことで、例えば2番仮登記を相続した場合、相続した仮登記は3番仮登記になります(実際には間に他の登記が入っていて、もっと後の番号になることもあります。)
そして、相続登記がなされても、元の仮登記が抹消される訳ではありません。例えば、2番仮登記を相続した3番仮登記を本登記にする場合、2番を本登記にしてから3番仮登記の本登記をする流れになります。そのため仮登記の移転をしても、元の仮登記が用済みになる訳ではありません。
ですので、3番仮登記(相続した先の仮登記)の抹消登記を申請した場合、この登記自体は問題なく可能ですが、このままでは単純に3番仮登記が消え、2番仮登記(相続する前の元の仮登記)は元々の状態で残る(と言うよりも、戻って来たような状態になる)こととなります。
仮登記の相続が間違いであった場合はこれで問題ないのですが、相続したのちに仮登記を解除等で、確定的に消滅させる意思であった場合、実体法上の権利変動を登記に正確に反映できてないことになってしまいます。(『不動産登記のQ
&A200選』(日本法令刊)231〜232ページ参照)
そこで、この場合、3番仮登記の抹消と合わせて、2番仮登記の抹消も申請する必要が出てきますが、先ほど説明したように仮登記の抹消には仮登記名義人からもしくは仮登記名義人の承諾が必要となっています。しかし、2番仮登記名義人は亡くなってしまっています。
私が調べた限りでは、上記の申請者権者について特例のようなものは見当たらないため、一体誰から2番仮登記を抹消できるのか、頭を抱えることになりましたが、『不動産登記の実務相談事例集Ⅱ』(日本加除出版株式会社刊)の237〜238ページによると、元々の仮登記と、相続により移転した仮登記は実体的に一体のもののため、3番仮登記名義人から2番仮登記の抹消申請が可能との記載を見つけることができました。
上記の記載は通達や先例ではないため、全国統一の取り扱いかどうかは不明です。実際の登記申請の際には、申請先の法務局とご相談されることをお勧めします。
今回のケースでは上記記載を基に法務局と打ち合わせの上、①2番仮登記の相続登記⇒②3番仮登記名義人(仮登記名義人の相続人)から2番3番仮登記抹消登記申請、という形で申請することで無事に仮登記の抹消をすることができました。
相続、仮登記抹消登記というあまり珍しくない登記手続きの中にも、意外な落とし穴が潜んでいたりします。日々勉強だなと痛感しました。
来年も是非たくさん勉強したいなと思っておりますので、ややこしそうな案件でも、もちろん単純そうな案件でも是非お気軽にご相談ください。